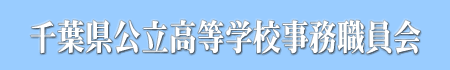「環境教育のめざすもの」
-その理念と動向-
環境問題については、大きく分けると地域の問題と地球規模の問題があります。
まず、地域の環境問題として最初に考えられるのが、公害問題です。さらに、廃棄、化学物質、原
子力の問題、交通問題などがあります。交通問題は、交通事故だけでなく、自動車による排気ガスの
問題があります。この排気ガスには、窒素酸化物や硫黄酸化物があり酸性雨の元になっています。ま
た、交通問題に関連して温暖化の問題があります。更に、自然保護、アメニティ、開発、歴史遺産、
過疎や過密の問題など、かなりの問題が環境問題に入ってきます。
そして、これらの地域における環境問題の総体として地球規模の環境問題があるわけです。地球規
模の環境問題には、9つの問題があります。そのうち、今、最も解決が困難な問題として温暖化の問
題があります。一昨年、温暖化を防止する国際会議が京都でありました。その時に、世界の先進国が
温室効果ガスの中で最も影響を与えている二酸化炭素を減らそうということで合意を得ました。また
オゾン層の破壊、酸性雨の問題、いずれも深刻な問題です。
その他、熱帯雨林の破壊や砂漠化、途上国における公害問題、そして、人口問題、あるいは食料の問
題など、いずれもこれら様々な問題が密接に関係して地球規模の環境問題を起こしております。
また、貧困の問題があります。これも人口問題と密接に関係し、特に、貧困の格差が年々拡大する
とともに貧困層の人口が増大していることも問題となってきています。
更に、人権、ジェンダー、平和等の問題がありますが、いずれにしても、これらの問題は相互不可
分の関係にあります。
現代は、持続不可能な時代といわれています。日本では、戦後50年、努力すれば報われる時代でし
た。
先に、中央教育審議会で、「生きる力」ということを提案しましたが、その中で、これからは「先
行き不透明な時代」と言っています。10年後、20年後はどうなっていくのだろうか。このままでいく
と、環境汚染や治安はますます悪化し大変な時代になってしまいます。このままでは持続不可能な社
会、これを持続可能な社会へと転換していかなければなりません。これが、地球サミットの最大のテ
ーマとなっており、また、この持続可能な社会への転換を、一刻も早く具体化していくことが、今、
私たちに課せられた大きな使令となっています。
1987年の国連での、「環境と開発に関する世界会議」の報告のなかで、「持続可能な開発」、即ち
「将来世代の選択肢を奪わない範囲内での現世代のニーズを満たすための開発」ということが提唱さ
れました。
この持続可能な社会の実現のために、環境問題や開発等多くの課題がありますが、現在の諸課題から
みて、
①世代内の公正、②世代間の公正、③種間の公正、以上3つの公正に整理することができます。
更に、持続可能な社会を考えていく際に、3つの持続性ということを考えていく必要があります。
それは、①生理学的持続性、②社会、文化、経済的持続性、③健康的、精神的持続性ということです。
そして、持続可能な社会を確立していくための視点として、地域的視点と世界的視点が重要な観点
とります。
人と自然との共生、循環型社会の実現、生物の多様性の維持など私たちの身近な諸問題を改善して
いく即ち、これが地域的視点です。
そして、私たちがこの日本の地域から世界の平如や人権、民主主義が保障されるように支援してい
くこのことがいわば国際理解に繋がっていくと考えています。
この地域の視点と世界的視点の二つの視点を持ちながら、持続可能な社会づくりに関わっていく、
このことが環境教育、環境学習なのです。
環境教育とは、簡単にいうと、「学習者と他者、あるいは学習者と自己を結ぶ営み、あるいは、繋
がりを意識させる営み。」のことです。
2002年から「総合学習」が始まりますが、これは「生きる力」を養っていくことを目的とした学う
です。
「環境教育」や「総合学習」の実践は、全て、「持続可能な社会づくり」に係わっていくことに繋が
ることなのです。