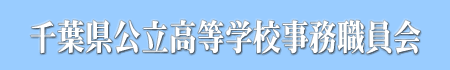「教育改革の動向」
今日は承りますと3300人を超える事務職員の皆様方が全国からお集まりになって、年に一度の大研
究集会ということで、そういう場所でお話をさせていただくことを大変うれしく思う次第でございま
す。
さて、事務職員の仕事というのは学校の顔だと、常々私は思うのです。先のご紹介にありましたよ
うに、私は広島県の教育委員会で2年余り教育長をさせていただいて、100程の県立学校をお預かりす
る立場になったわけでありますけれど、その時よく学校現場を訪ねて行きますと、どの学校も玄関を
入って最初にあるのは事務室ですよね。まず事務室にこんにちはと言って入って、帰るときは事務室
の中を覗かせていただいて、事務室の中はこんなになっているのかと言って帰っておりました。
ところで、学校の応対はだいたい決まってますよね、まず入っていくと校長室に通され、そこで校
長先生から学校の教育方針などの説明を伺うわけなんだけれども、その時も、広島のいろんな学校で
事務職員の方々がいろんな心づくしのもてなしをしていただいて、「これはこの土地の名物なんです
よ」ってお菓子があったり果物が出たり、校長の話はあまり覚えてないんですけれども、もてなされ
たことはよく覚えておりまして、校長さんの話を開きに行ったというより、事務職員の皆さんにもて
なしてもらうために行ってたんじゃないか、と言うのは冗談で、その学校訪問で大事なところは、校
長先生の話は5分位で終わらせてもらって、とにかく学校の中を見せてもらい教職員の皆さんや子ど
もたちと話をするということであったわけです。
ところで、やはり事務室は学校の顔であるということは大事なことで、これは昔から、おそらく50
何年前から変わらず言われていることだと思います。今日この大会は52回目だと聞いてますけど、52
年前にもおそらく同じことを言ってたんだと思います。だから事務室が学校の顔であることは昔から
変わらないんだけど、顔が大事になってきたということが大きな変化なのです。前は頗なんかどうで
もよかったわけです。顔がどうかということよりも中身だ、というようなことで学校の評価というの
は、学校の教育内容じゃないか、学校の顔は別にそんなに綺麗にお化粧してなくてもいいとか、ある
いは学校の顔はとにかく首の上にのっかてればいいんだというようなことだったんでしょうね、顔じ
ゃなくて心だよ、顔じゃなくて頭だよ、みたいなことで学校をやっていたんです。勿論学校の中にお
ける心の部分、あるいは頭の部分がどうでもよくなったというわけではなく、顔も大事だよと言うこ
とになってきたのです。今までは学校を取り巻く社会の皆さん方が、学校の顔はどうでもいい、例え
ば学校に電話を掛けたときの愛想が良くなかったとかそんなことはどうでもいい、いい教育さえして
てくれればいんだというわけだったんでしょうけど、今の時代になってくるとその顔がどうでもいい
というわけにはいかない、これが非常に大事なものになってきたのです。その心や頭は依然として大
事なことであるんだけど、今まで顔はあまりそんなに大事にしなくていいと思っていた、その顔の部
分が大事になってきたということは学校にとっての顔である事務職員の皆さんの役割が非常に大きな
ものになって来たんだというように認識していただかなければなりません。
なにも学校だけじゃないんです、文部省だって今までは顔なんかどうでもいいと思ってた、文部省
がよそからどう見えた方がいいだろうかなんてことは考えもしないでよかった、文部省は綺麗に見え
なくてもいい、文部省の中にある頭と心がちゃんとしてれば文部省という顔は綺麗にしなくてもいい
あるいは顔を見せなくてもいいと言ってた訳です。だけど今はそうはいかない、さっきちょっとご紹
介にあったように私は今、文部省の政策課長という立場にありながらテレビに出てお話をしたり、あ
るいは新聞や雑誌で討論したり、あるいはいろんな場へ出かけていって、今日は身内の教育界の集ま
りでございますけれども、一般の市民の方々のお集まりに出かけていって話を申し上げる、あるいは
JAの集まりに行ってお話をしたりします。そういうことは、昔の文部省の役人には必要のないことだ
と思われてました。このように文部省は顔を見せる必要はない、文部省の顔はこうなんですよ、私の
顔を見たってしょうがないんだけれど、文部省はこんな所なんですよということを一生懸命外に向か
ってPRする必要はなかったのです。
今、そうでしょう、皆さん方の学校でもそれぞれ学校を知ってもらうパンフレットを作ってますよ
ね、昔は作ってなかったですよ。ここに、この学校があるから皆来るのが当たり前だ、中学生たちは
高校に行きたいと言うだろう、障害を持った子どもさん達も障害児学校に行きたいと言うだろう、と
にかく皆来たいんだろう、来たいんだったら入れてやるよみたいな考え方でやっていたんです。でも
最近はそうじゃない、うちの学校はこんなですよってことをPRしていかなきゃいけない。だから学校
の顔っていう意味は学校をPRすることでもあるわけで、文部省もPRをしていかなきゃいけない。
最近、特に5月6月頃は文部省の中に中学生や高校生の姿がいつもあります。これは、修学旅行で文
部省を訪ねてくるのがこの頃多くなっているのですが、多くなったというのは来たい人が多くなった
というより、文部省が今までとても修学旅行を受け入れるなんてことは考えてもいなかったのですが
修学旅行の皆さん来て下さい、中学生高校生あるいは小学生でも文部省が見たい方は、どうぞどうぞ
ということになってきたのです。
これはまた学校でもそうですよね、今までは学校公開っていうのはあんまりやってこなかった、け
れども学校を見て下さい、あるいはうちの学校の子ども達はこんなことをやってますよ見て下さいと
。これも顔です、特に教員の皆さんに学校のPRをと言うと、PRなんか学校に必要ないんだというよう
なことを昔は言っていた。でもうちの学校はこんな学校です、うちの子ども達はこんないいことやっ
てるんですということを知らせていくということは大事なことなんです。だから文部省も修学旅行は
受け入れるはずですね。
先週はインターンシップというんで高校生、大学生の文部省職業体験というのを募ったら、大学生
しかこないだろうと思っていたところ、高校生の応募者が4人来ました。神奈川県の高校と山口県の
高校だったですかね、4人高校生が文部省で一週間働いてみたいなんていうように来ました。また、
夏休み中には今度は中学生以下を対象に文部省見学デーとか見学ツアーみたいなのを作っていく。子
どもに対してだけじゃありません、皆さん方も、もうOA化が進んでどの職場にもコンピューターがあ
るでしょうから、まだ経験のない方は試してください、文部省ホームページというのがありますから
それにアクセスしていただくと文部省で今こういうことが考えられている、今度こういうことを発表
したなどということが、全部ホームページを通してアクセスした人に伝わるようにしていく。更には
この6月からは子供ホームページていうのも作って、文部省のホームページの中に子供がアクセスす
る部分というのも作っていったりもしています。
それから、これは新しいのでご存じないかもしれませんけど、これも6月からエル・ネットという
情報伝達手段を文部省の方で作りました。これは分かりやすくいえば、文部省の中に放送局ができス
タジオができたのです。そこから各学校、あるいは各教育委員会、あるいは公民館、というようなと
ころに衛星放送で情報を伝達できるシステムが作られています。だいたい全国五千カ所位に、受ける
ところ、例えば各都道府県の教育センターみたいなところには必ず受像装置が付いています。そうす
ると、今までだったら文部省の課長とか教科調査官とか、そういう人の話を開くには、その人を、私
がここにいるように、ここまで連れてこなければいけないから、なかなか大変だった。でもこれから
は、文部省のスタジオで、私たちがお話しすれば全国の学校や教育センターでも見ることができるし
実はこれまた、ただ見るだけじゃなくてですね、そっちの方からも質問したりできるような及方向性
の通信システムとしてやっているんです。これをエル・ネットと申します。もうだからすでに例えば
都道府県の教育委員会の中にその装置を付けていただければ、何時でもお話ができるんです。そうい
うように文部省も教育委員会も学校も顔を見せていくことがとっても大事な時代になってくると言う
わけであります。
私は、これからは事務職員の時代だ、というようなことを言いますけど、今日は、事務職員の集ま
りだからそう言っているのかもしれない。実は、教頭先生の集まりに行くと、これからは教頭の時代
だ、とこう言ってんですよ。だけどですよ、校長さんの集まりに行ったときに、これからは校長の時
代だとは言いません。
つまり、今までのように校長が一人で、私が校長だ、校長が全部やって行くんだ、という時代じゃ
ないんだと言うことです。校長先生の両側に、教頭さんと事務長さんがしっかり付いて、校長、教頭
事務長という、この三つの鉄の三角形みたいなのができてですね、この形態で学校を運営していく。
校長さんがやっていて、教頭さんや事務長さんは校長さんの陰にいる、という時代じゃない、教頭さ
んも実は、なぜ大事かというと、いわば教員スタッフの中では、学校の顔になるべきで、PTAの対応
とか、外からの苦情がきたときの対応とかを、教頭さんがする部分がございます。つまり教頭さんと
事務長さんというのは、学校の対外的な顔の部分を代表している。校長先生は、勿論学校そのものを
代表しているから、何かがあって、どちらかといえば校長さんは、名誉のあるかっこいい場所に行く
のが校長さんの役目で、式典だとかに何々高校の校長ですとか、何々養護の校長ですと行くのが校長
さんの役目です。そうじゃなくて住民から、学校のことはどうなっているのか、聞かせてくれとか言
って申し入れがあったとき、それに対応していかなければいけない、あるいは学校に電話がかかって
きて、これはどうなっているんだ、と言われたときの対応、そういう外の顔をしていくっていうのが
教頭さんと事務長さんに求められていることだと思うわけなんです。
だから、実は私は教育長してるときも努めて校長だけが中心の学校運営は良くないと思ってきた。
例えば、年度始めになんかに校長会の集まりがあり、懇親会とかあります。校長会の集まりには教育
長が行くんだけれども、事務長会とか教頭会は部長が行けばいいだろうみたいな話があるけどそれは
おかしい、どの職も大事な学校を守ってもらう仕事なんだから。教育長時代の私は、校長会に行くの
は当たり前の話だけれども、教頭会にも行って膝詰めで懇親会まで出て話をしたい、事務長会でも、
そういう話をさせてもらわなければいけないと思っていました。
ですから、そういうように教育委員会や文部省も、考え方を変えていかなければならない。とにか
く、立派な校長さんさえ作っていけば学校が回っていくという問題じゃない、校長を支える教頭、事
務長、更にはさまざまな主任さんたちが、チームプレーで学校を運営していく、勿論、そのチームプ
レーをやっていく、いわばその中での長としての、校長のリーダーシップは当然必要なんであって、
校長がどうでも良くなったと言ってるわけじゃないんです。校長さんは昔と同じくらい大事、だけど
教頭さんや事務長さんは昔くらいの大事さ加減じゃとてもだめだ、もっと大事な存在だと周りも認め
ていかなければいけないし、ご本人もそれだけの自覚を持っていただかなければいけないと言うこと
なんだろうと思います。勿論、その事務長さんを支えていくのは事務室の全事務職貞で、自分たちも
この学校を支える重要なスタッフであるという自覚と意識を持って進めていくということが、必要で
はないだろうかと思います。私は、広島県から文部省に帰ったら医学教育課長というのをやっていま
した。これはまた、いろいろな仕事があるのですが、その中の一つに、全国に43の国立大学医学部と
13の歯学部があり、その、それぞれの国立大学付属病院を運営していく仕事があったんです。これも
なかなか運営にいろんな問題がありました。国立大学付属病院は、普通の病院みたいに儲かる診療を
してないわけですから、いわゆる診療費で、あがってくる収入というのは4割そこそこで赤字が出て
くる。その半分以上の赤字は国民の税金で埋めてやっていっているわけです。よりよい運営をしてい
くっていうのは、例えば広島県の県立学校によりよい運営をしていくというのは広島県民の皆さんの
為にそうしていかなければいけないし、国立大学付属病院は皆さん方も含めた全ての日本の納税者の
ために運営していかなければなりません。やはり、同じなんです国立大学付属病院も。行ってみると
院長先生が立派でいいんだけど、そこをやっていくには三つの仕事があります。県立学校の場合には
そこにいる職員は、教員とそれ以外の一般職員と技術系職員の三種類で、付属病院も同じなんです。
みんなが先生と呼ぶのが、お医者さん達で文部教官、大学の先生ですから教官と呼びます。それから
看護婦、臨床検査技師等様々な役割の技術職貝の人たちがいる、国の場合は技官と言います。それか
ら、皆さん方と同じように国立大学付属病院にも事務職員がいます、事務官といいます。教官と技官
と事務官、この三つの職種で運営されているのが国立大学付属病院です。そうだとすると、今までの
国立大学付属病院というのは、教官ばかり発言権があって、教官がこの病院を担っているんだと言う
意識があって、技官や事務官は1ランクも2ランクも低く扱われたり見られていました。これではだめ
だと、本当にいい国立大学付属病院を作っていくためには、技官が元気を出しくれなければいけない
事務官が元気を出してくれなければいけないということを言ってきました。それは顔だという問題も
ありますけど、それだけじゃなしに本当は心や頭の部分も、それは教員がやっているから、事務職員
や技術職員は関係ないということじゃないと思います。その学校の中に、あるいは病院の中にいる全
てのスタッフが、学校の、又は、病院のカを高めるために役割を果たして行くんだということを、明
示していかなければいけない。
学校の中で、学校運営に関する会議に事務長さんが出られないなんてことは、まずないと思います
けど、国立大学付属病院の場合は往々にして、教官だけで、その病院をどうするかということが、決
められる場面すらあります。これじゃだめだ、病院のことをどうするかを決めるときには、教官と事
務官と技官の代表が出て、みんなで議論をしていかなきゃいけない、事務官を代表するのは事務長、
技官を代表するのは看護部長といって昔の看護婦長さんで、教官である医院長と、技官の代表である
看護部長と、事務官の代表である事務部長が、やはり三位一体でやっていかなければいけないという
ように、これは、実は県立学校を、どうするかを考えていったのを応用させていただいて、実は、県
立学校より国立の方が遅れているわけで、国立大をどうするかという問題に、応用させていただいた
と言う訳なんです。
さて実は、その国立大学でありますけれども、今、国立大学の歴史というのは明治以来、明治の初
めに帝国大学ができて以来あるんですけれども、歴史始まって以来のピンチに、今見舞われているん
です。国立大学のうち、4分の1ぐらいはなくせということが言われています。今、その国立大学のピ
ンチを誰が守っていくのかというと、教官達はその時どうしていいのか分からなくなってしまう。ま
さに今、各国立大学で事務官たちが、いったいどうしたらいいんだろう、どうやったらうちの学校は
生き残れるんだろう、うちの学校の価値を認めてもらえるんだろう、つまり教官達も、勿論がんばっ
てもらわなければいけませんよ、学校の価値を認めてもらうためには。
例えば、ここには高知大学と高知医科大学という国立大学があります。その価値を認めてもらうの
は、そこでいい教育をするということが大事なことで、それは教官がやっていかなければならない。
しかし、ただいい教育をしてるぞと言っても誰も納得してくれないいんです、そのことを、みんなに
説明しなければいけない。これを、最近流行っている言葉というか、最近大事になってきている言葉
にアカウンタビリテイ、日本語になおすと説明責任という、学校のやっていることを説明する責任が
あるんだよと言う訳です。
今、国立大学では、学校の教育をしていくのは教官なんだけど、説明責任を果たしていく役割って
言うのは、教官の先生方にはできにくい、事務局がその説明責任をしていかなきゃいけない。皆さん
方だってそうでしょう、学校の予算はこれだけあります、この予算は本当に有効に使われているんで
すよと、説明していかないと税金を無駄遣いしてるじゃないかと言われる。昔の納税者の皆さんは、
自分の税金をお国にお預けしとけば、あるいは県にお預けしとけば、ちゃんとうまく使って下さるだ
ろうと思って無条件で預けてくれてました。
今、そうじゃないでしょ、ここにいらっしゃる皆さん方だって、学校で働いてらっしゃるけれども、
税金は当然払ってますよね。その払ってる税金が学校で使われるのは、自分たちが学校で働いている
から、当然のことだと思われるかもしれないけど、例えば、今の福祉の在り方なんていうのは、これ
でいいのかと思ったときに、自分の税金これでいいのか、あるいは、でたらめなことをやっていた銀
行を救うために、自分の税金が使われているけど、それはそれでいいのかと思ったときに、もうそれ
は、大蔵省に任せますなんて思わないでしょ。ちゃんと説明してくよ、責任を取るべき人間は取って
くれよと言っているわけです。
同じように、同じようにと言っても悪いことをした銀行と学校を一緒にしているわけじゃないけれ
ども、税金を使う場所である以上、皆が納得できるような説明をしていかなければいけない。これだ
けの税金を使っただけの価値のある仕事をしていますよ、という説明をする必要がある。この説明責
任を果たしていくということが大事なんだ、だから、顔を見せるというのは、顔を塗りたくって綺麗
に見せようということじゃなくて、私の顔はこうなっていますよ、あなたの税金を使った結果、この
学校の顔は、このようになっていますよということを、見せていく必要があるという意味なのです。
その意味で、学校の顔たる事務室の役割、あるいは事務方の役割ということが大きくなってくる。
でも実は、国立大学はピンチが迫っているけれども、県立学校だって子どもの数が減ってくる中で、
統廃合の話なども出てきますよ。それから、まだ全国的にではないけれども、例えば、東京周辺を中
心にして、私立の方に子どもが行ってしまって、子どもはいるんだけど、私立に行っちゃうから少子
化以上に公立学枚に来る子どもの数が減ってしまって、もう公立学校はなくてもいい、私立に行きゃ
いいじゃないか、みたいなことがあり、そういう形で過疎化とか、少子化とか、あるいは私立が非常
に人気が出てくるということの中で、公立学校が、なぜ必要なの、どうしてこれがここになきゃいけ
ないの、そこにみんなの税金を使ってやっているのはなぜなの、ということになってくるのです。
だから今、国立大学がどうなるかってことを、皆さん方もよく見といてほしい。その議論がどうな
るのか、でも皆さん方だって、国立大学にあんなに税金を使って、いいかどうかっていうのは、考え
て見た方がいいですよ。いや、私は勿論、文部省の中で、その国立大学が必要だという説明責任を果
たしていく立場にあるから、皆さんが、国立大学はたくさんあってもいいじゃないか、と思ってくだ
さるのはありがたいけれども、よく考えた上で、そう思っていただくのが一番うれしい訳で、なんか
わかんないけど、いいだろうといわれるよりは、よく考えたよ、おまえたちが説明するから、国立大
学の中身をよく見てみたよ、なるほどこれは必要だなと思ってもらうことが一番いいんであって、そ
れをごまかしたり、隠したり、だまかしたりして、国立大学はよくやってますから、私に任せて下さ
いとか言って、やっていって、いわば上辺だけの信頼を勝ち取っていくよりも、本当の中身を見ても
らって、なるほどこれはすばらしいなと思ってもらう、本当の信頼を勝ち取っていく行政をしていか
なければいけない。それが今、国立大学に求められているってことは、各都道府県のレベルでは各都
道府県立学校でも追々求められてくる。
一番きてるわけです。公務員の数を25パーセント削減しなければいけないなんてことも、国では決ま
っているんですね、10年以内に公務員を25パーセント削減する。あるいは、できる限り国立の機関を
なくしていく、独立行政法人という名前を聞いたことがあると思いますけれども、独立行政法人にな
るか、民営化するかということです。これは、別に遠い未来の夢物語の請じゃないんですよ、皆さん
方の県にも、おそらく国立少年自然の家とか、青年の家とかが、あるところが多いと思います。この
高知県にも、国立室戸少年自然の家というのがありますが、あれは、後2年で国立ではなくなります。
もうあそこは国立施設じゃない、あそこにいる職員は国家公務員ではない、独立行政法人としての、
しかも、非公務員型の独立行政法人としての、室戸少年自然の家というのになるということは、もう
決定しているんです。そうなると、今までと違って、公務員じゃありません、公務員型の扱いを受け
ませんから、業績評価をきちんとされる、それから、その少年自然の家自体の収支バランスシートと
いうのを出していかなければいけない、どれだけの収入を上げているのか、どれだけ利用者がいるの
か、全然利用者がいないんだったら、そこにはもう予算は付けられないよ。独立採算でやれと言って
いる訳じゃないんですけれども、国が補助金を出すけれども、ただ出すんじゃなくて、成績が良くな
かったら、もう補助金出すのを打ち切って、そこは潰してしまうよという様なやり方で、一年一年真
剣勝負で、その少年自然の家をどうするかということを、問われていく訳なんです。
同じように、国立大学もなくせという訳じゃないけれども、私立大学と同じように自分で責任を持
って、運営をするようにしたらいいじゃないか、ということを言われている。そらそうでしょう、私
だってね一納税者の立場になると、こんなにたくさんの国立大学に私の税金が使われるのはいやかと
いうと、いやです。職業上そら私は仕事として、これは大事ですとは言いますけどね、今のように授
業中携帯電話は鳴る、携帯電話が鳴ったから慌てて切るかと思えば、「あ、もしもし元気」とかいっ
て話す学生、それから私語ですよ、今日は皆さんこうやって黙って開いていただいてますけれども、
大学の先生達に言わせると、あの私語っていうのが波のように広がっていくらしいんですね、この辺
でしゃべり出すと、ざわざわざわざわっと、その私語の渡っていうのが起こったら、5分くらいは手
が付けられないというようなことを言います。
この間、東京学芸大という教員養成大学の先生が、自分は定年退官したので、今までは言えなかっ
たけど、退官したから言うけど、ということで開いたのですが、教員養成大学の授業が成り立たない
んだもの、だから、その大学を出た先生が小学校で、授業崩壊とか学級崩壊とかいうのも当たり前だ
ろうと。教員になる大学の学生が全然講義を聞かない、授業を成り立たせない、というようなことに
なっている。
教員養成大学の名誉について言えば、他だって同じです。例えば医学部の学生なんていうのは、人
の命を預かる医者になる訳だから、さすが一生懸命勉強しているかというと、これは全然授業は聞い
てない、100人のクラスで5人しか授業を開きに来てないなんてことはざらなんです。95人は何
をしてるかというと、医師国家試験に要領よく合格するための塾の方に行ってるとかそういうことに
なる。そんならもう国立大学医学部に、莫大な国費を投入してやる必要はないじゃないですか、医師
国家試験というものがあるんだから、それの予備校みたいな所に自分の金で入って、やってもらった
らいいじゃないですか、という気になりますよ。ものすごい、お金を使って授業をしているのに、1
00人中5人しか開きにこない、これは実話です。私の従兄弟が、ある国立大学医学部の教授をして
いるんですけれど、彼が言ってました、「いや5人も来てくれりゃいいほうだ」と。全部の授業が、
そういう訳じゃないけれども、特に大事な、上辺の診療の技術が身に付くのには来るんだけれども、
いわゆる基礎というやつ、病理学とか細菌学とか、そういう基礎の学問のところの授業なんていうの
は、特に顕著だとよく開きます。
かくいう私も、東京大学教育学部と東京工業大学の大学院で授業をしたんですけれども、これがひ
どいんですね、東京大学教育学部の授業をしたときにはみんなが無気力なんです。よく無気力なこと
を、死んだ魚の様な目をしているって言うけれど、死んだ魚のような目をしている、50人に話をし
てる私も非常に情けなかった。興味がないなら来るなよって思うんだけど、何で来るかっていうと、
こないと単位もらえないんですか、と開くとそんなことはない、じゃあ開く気がないんなら、来るな
よと言ったら、こないと不安なんだそうですね、授業は聞きたくないけれど、授業に行かないと、皆
から落ちこぼれるような気持ちになるから、皆と同じことをしなけりゃいけない、だから東大みたい
な大学は出席率はものすごくいいんだけれど、講義を聞いているものはほとんどいないんだと、これ
は学生にも開きましたからよく分かりました。私の授業だけじゃない、どの授業も皆授業を聞いてい
ない、聞いてないなら来るなよって言ったら、皆と一緒のことをしてないとすごく不安だからそこに
は来るんだけど、そこで行われてる授業には全然興味を持ってない、高等学校の進路指導の先生達に
一回授業を見てもらいたいですよ、偏差値が君はちょうど東大教育学部というか、東大の文Ⅲにあた
るから、そこに行きなさいと言われて行ってたんでしょうね、何でここに来たのって言えば、彼らは
別にって、言うでしょう、偏差値が東大の文Ⅰ、文Ⅲには足りないけど文Ⅲだったら入るからづて、
そこへ行ったんでしょうね。東大はまた入ってから学部振り分けというのがありますから、ちょうど
また学部振り分けする時の成績が文学部には行けなかったから、まあ教育学部、みたいなことで来て
いる、全部が全部そうじゃないですけど、そういう思いで来てれば、普通ね。
私が話しに行ったのは、教育学部の教育行政の授業ですよ、日頃教育行政の授業を開いている人が
今日は現役の文部省の役人が来て話をするから開く、教育行政を本当に勉強しようとしている学生だ
ったら文部省の人が来たら、どんな人なんだろう、腹黒い悪い奴なんじゃないか、権力を振り回して
皆を押さえつけようとしてる奴じゃないのかと思うか、あるいはすごい人と思うかどうか知らないけ
ど、興味を持って見るはずじゃないですか、皆全然興味がない。教授が、せっかく現役の役人が来て
いるんだから質問責めにしていいぞと言っても、質問する学生は一人もいない。これが、今の東大教
育学部の授業ですよ。ここに国費を投入する価値があるのかどうかということです。かろうじて大学
院の学生が何人か来てて、彼らは一生懸命質問しました。彼らは、文部省の人が来るんだったら、是
非自分たちも聴講させて欲しいと言って来てて、学部の授業だから、まず学部の学生が優先だからと
自分たちは遠慮してて、ところが、学部の学生は誰も質問しないから、大学院の学生が一生懸命開く。
でも、この大学院の学生のうち、大学が東大だったという学生は半分もいないんです。皆他の大学で
やって、もっと勉強がしたいという意欲を持ってきている。
今大学院に入っている学生は、勉強しようと言う意欲に充ちていますよ、だから、私は自分の税金
が大学院に使われることは悪いとは思わない。大学は、3分の2の勉強しない学生がいるわけですから
私は3分の2位は税金をどぶに捨ててると言われてもしょうがない、申し開きができない。なんでこ
んな勉強しない奴のために、俺の税金を使わなければいけないのって、言われたらうまく説明できな
いですよ。勿論四六時中勉強してなきゃいけない訳ではないですよ、大学生ともなれば、いろいろ自
分で考える時間があったり、自分で本を読む時間があったり、そう言うのならいいんですよ、そう言
うのならいいんであってそんなら教室に来てぼんやりしてないで、自分でどっかでスポーツを一生懸
命するとか、あるいは文学を語るとか、哲学を探求するとかいうことをやりゃいいじないですか、こ
れじゃあとてもじゃない。だからそういう大学だったら潰されてもしょうがないという自覚を持つ、
じゃあ潰してもいいですよっというんじゃなくて、そうじゃない大学にしていこう、全ての学生が勉
強していく大学にしていこうと。
不思議ですよね、小学校、中学校、高等学校ではですよ授業中に携帯電話鳴らしてなんていうこと
はまず希ですよね。あるいは、授業中にお喋りをするとか、そういうことはまず希ですよね。大学に
なるとそれが全然歯止めが利かない、同じ子供ですよ。ついこの間まで高校で学んでた時は、先生の
授業一生懸命開いてやってたんでしょう。大学に入ったら不思議ですよね。高校の授業というのは残
念ながら、これから教育改革していかなければならないけれど、今までは先生の側から一方的に与え
られる授業だったんですね。自分がそれを、受けたかろうが、受けたくなかろうが開かなきゃいけな
い授業だったんです。その時は一生懸命聞いててですよ、大学というのは自分が学びたいことを自分
で選んで自分がこの学部の勉強がしたいから、この授業がとりたいから、この先生の講義を聞きたい
からと思って開くのが原則の学校のはずなのに、そこで全然授業が成り立っていない、何のために勉
強するのか、ということがまるで分かってないんです。
まるで分かってないのは、その大学生たちが悪い訳じゃなくて、彼らをそれまで育ててきた私たち
大人たちで、家庭や小・中・高等学校で大人たちが、みんなで寄って集って、18歳までに勉強を嫌い
な人間にしてしまっているからです。子どもたちに開けば分かりますよ、なぜ高校の時は授業を一生
懸命受けているのに、大学に入ったらしないのか、だって高校ではやらないと先生に怒られるもの、
高校の授業で授業中携帯電話で話してると先生はやめろって言うでしょう、大学の先生はやめろって
言わない人が多いんです。高校の先生はお喋りしている生徒がいたら、お喋りをやめろ、あるいはそ
こに立ってろと言うでしょうけど、大学の先生はお喋りしてても全然関係なく自分の講義をやってい
っている。だからまず今大学に言わなきゃいけないのは、授業を変えていく。それから、本当に学ぶ
心を持った学生を育てていくということもあるけど、それ以前に、先生はちゃんと学生を注意してく
れ、ということを言わなきゃいけない。で大学の先生が注意しないのかって思うでしょう。小・中・
高等学校の先生は、教育だけが仕事だからです。自分の仕事は教育だと思ってますからね。自分の仕
事は教育で、自分の仕事は授業だと思ってるから、その授業が成り立たなかったら自分が否定される
思いがするでしょう。誰だって自分が否定されるのはいやだから、「やめてくれ」とこう言いますよ
ね。大学の先生は、教育が自分の仕事だと思ってない人が多いんですよ、仕事の一つではあるけれど
も、自分の仕事で大事なのは研究だと、研究をすることが自分の大事な仕事であって、教育はやらな
きゃ仕方がない、授業もやらなければいけないからするけれども、大半の先生にとっては授業はやら
なければいけないからするものだ。研究は自分がしたいからするものだ。だから研究の邪魔をされた
ら、ものすごく怒るでしょうけれども、授業の邪魔されたってまあいいや、仕方がない、言ったって
しょうがないと思っている。これが、大学の先生に根本的に改めてもらわなければならないところな
んですね。研究も大事な仕事だけれども、教育も大事な仕事だと、認識を持ってもらわなきゃいけな
い。研究が主で、教育が従だなんて思ってたんじゃ困る、ということは言っておかなければいけない。
ただ、もう一つの要素は、高校まではただカで押さえつけていたんじゃないのか、ということなん
です。そんなことをやると卒業させないぞとか、そんなことやると単位やらないぞとか、こんなこと
やらないと高校出してやんないぞみたいなことでやっていたんじゃないか。だから高校生達は本心か
ら授業を聞いているのか、どうかというのは疑わしいものがあるりますね。聞いてないと怒られるか
ら、聞いてるのかもしれないです。少なくとも、大学生になったら急に勉強が嫌いになったというこ
とは考えられないんですけどね。そこのところを、これから、きちんと考えていこうというのが教育
改革。今、進めている教育改革の在り方なんです。
実は、小中学校だけが大きく変わるということだけが、マスコミでクローズアップされていますよ
ね。小中学校は、教育内容を三割削減して、基礎基本に徹底して、総合的学習を取り入れて、一人一
人の個性が伸びる教育をしていこうじゃないか、というような言い方をしています。
高校がどうなるのか、あんまり高校は変わらないかのように思われているけれど、とんでもないで
すよ、高校こそドラスティックに変わっていってもらわなければいけない。ただね、なぜそれが表に
出てこないかというと、小中学校というのは、基本的には地方分権で各市町村が責任もってこれから
やってく方向になるけれども、義務教育なんだから、あっちとこっちであんまり違ってることをする
ってことはありえないですよ。小中学校は、義務教育段階だから、何処でも大体同じ位のことをやら
なきゃいけない、ということが決まってます。高等学校や障害児学校は、各都道府県がそれをどうす
るか決めていく、極端に言えば、日本中だったら47通りの県立学校の考え方っていうのがあっていい。
だから、あんまり文部省がこうなりますよ、ということは言えない。文部省が、こうしますというこ
とを言えない。文部省に対して、「これからの小中学校はどうなるんですか。」と質問されたら、こ
うなりますといえます。文部省が学習指導要領も、かなり細かく定めているし、「こうですから、こ
れからの小中学校はこうなります。」といえます。私は、「これからの高等学校はどうなりますか。」
と開かれたら、「こうなります。」とは言えません。広島県の教育長をしてるときは言いますよ、
「広島県の高校はこうなります。」と。文部省の立場から言うと、「こうなるでしょう」とか「こう
なると思いますよ」としか言えない、「こうなると思いますよ」と言うのを、今から言わせていただ
きますけど、びっくりする人もいるかもしれないし、なるほどそうなるだろうと思う人もいるかもし
れない。
私は、例えば高校進学率が下がり、中退率がものすごく高くなる、というように予測しています。
それは悪いことなのかと言われると、悪いことじゃない、いいことです。本当に学びたい人だけが高
校に来る、勿論大学も同じです。高校と大学は同じ、基本的な考え方で、本当に学びたい人だけが来
て欲しい、学びたくない人は高校に来る必要はないということ。あんまり学校現場で重大に受けとめ
てないかもしれませんけれども、つい一ケ月前新聞には大きく載りましたけれども、文部省がこうい
うことをしたよということが出てました。大学院の入学資格を撤廃すると。今まで大学院は、大学を
卒業してないと、入学資格はなかったんです。でもこれからは、それまで一切学校に行ってない人で
も、勿論大学院には入れるカがあるかどうかは、試させてもらわなければいけないけど、でも入学資
格は問わない。それから、大学についても、大学入学資格検定試験を受けてもらえば、それまで高校
に行っていようがいまいが、中学枚に行っていようがいまいが、大学入学資格を得ることができると
いうようになりまして。これは、実はすごく大事なことなんです。今までは、高校に行ってなきゃ大
学に行けなかった、中学校に行ってなきゃ高校に行けなかった、小学校に行ってなきゃ中学校に行け
なかった。つまり、大学に行こうと思ってたら、小中高等学校に必ず行ってなきゃいけない。行かな
くてもいいよ、行かない道もありうる、大学院に至っては誰でもいいよ。さっきも申し上げましたよ
うに、大学院こそが今、真の本当に学びたい人だけが集まる場になっている訳ですよ。大学院以外の
所は全部そうじゃないと、私はこの学校で学びたい、この授業を受けたいと思って来てる、というこ
とにはなってないと思います。
そうすると、実はなぜ高校に来るのという話になるんですよね。実は、勿論こういうご心配をなさ
っている高等学校関係者も結構いるんですよ。そういうように高校を経なくても大学に行けるように
なったら、高校なんか行かなくてもいいと思う子供が増えるに違いない、増えるでしょうね。でもそ
れはね、もう一度考えてみなけりゃいけない、大学に行くために高校に行く、なんていうのは間違っ
た考え方なんですよ、高校に行くのは、この高校に来て、あるいはこの障害児学校に来て、ここに来
て、ここで学びたいから来てるはずなんでしょう。この高校には別に入りたいわけじゃないけれども
大学には行きたいからしかたなく我慢して、三年間ここに来てるんだよ、といって高校に来るのはお
かしい。高校の教職員の皆さんだって、そんなことで来る生徒を気持ちよく迎えれるなんて変なんで
す。我が学校に来たい、ここで学びたい、この学校ではこんな活動ができる、何か次の資格を得るた
めだけに来るんだったら、学校の持つ意味はないです。
だから、このことによって文部省は、学校制度のことは文部省が決められますから、文部省が、こ
ういうように制度を変えたというのは、二つ意味を持っているのです。まず一つは、子どもたちに対
して、何で高校に行くのかしっかり考えてくれよ、何で大学に行くのかしっかり考えてくれよ。それ
をちゃんと考えてない人を、今までは、高校に行かなきゃ大学に行けないんだから、我々も高校に行
かしてくれよと言われたら、無理にでも入れて、全然勉強しない子にも卒業証書を出したりしてた訳
でしょう。そんなことはもうしないよ、本当にここで勉強しようと思って、それだけの力を付けたら
卒業証書を出すけれども、そうでなかったら出せないよ。だから、高校に入るということの意味を、
君たちもちゃんと考えてくれよ、大学にはいるということの意味をきちんと考えてきてくれよ、それ
だけの自信と覚悟がないんだったら来ないでくれよ、ということを言っています。
もう一方では、今度は高校や、大学に対して言ってるわけです。今までは、そこに来なければいけ
なかったから、来てくれてたんだけれども、そんなら来なくなるような高校なんだったら、それはい
ったい何だったのかということ、大検に合格して大学へ行けますから、もう高校には行きませんと言
われるような高等学校だったら、そら何なんだと。高等学校は、大学に行くためだけの機関じゃない
でしょう、予備校や塾との違いは何なんですか。そこで育まれる友情、先生との人間関係、あるいは
そこでスポーツをやること、いろんな生徒会活動をすること、いわゆる学生生活、高校生活があるか
らなんでしょう。それに意味がないと思われたら、試験だけを受けて、大検で入っていけばいいじゃ
なかってことです。
魅力ある高校生活、あるいは魅力ある大学生活、授業から部活から生徒会活動からあらゆることを
含めて、魅力ある高等学校生活を提供しているんだろうか、魅力ある大学生活を提供しているんだろ
うか、ということを問い直してもらわなきゃいけない。今まで高校という名前に、大学という名前に
寄り掛かってやっていた部分をなくしてもらいたい。本当に価値ある学びの場か、学びの場でないか
は生徒が、学生が選んでいくという時代に突入していくということです。
よく高等学校の先生方は、高校が一生懸命やっても大学が変わらないからって言いますけど、今言
っていることは高枚も大学も同じこと、皆さん方どう思ってらっしゃるか知らないけど、今時、学歴
社会と言いますけど。一般的に私たちの生活している官庁だって、東京の企業の人たちと話していた
って、この人が大学を出ているから、ということで人を評価することは有り得ません。私は大学を卒
業いたしましたって言ったって、この人が勉強しているかどうか、皆疑いますよ、勉強をしてない学
生が3分の2いることを誰だって知っているわけだから。「私は○○大学を卒業いたしました」と言っ
ても、どれぐらい勉強しているか分かりません。学歴っていうのはね、悪いことじゃないんですよ、
学歴を否定する必要はないと思います。学歴が、変な意味で使われることは否定していかなければい
けない。だから学歴社会が悪い訳じゃなくて、学歴社会の弊害というのがよくない、学歴は、それな
りに評価する必要がある。だけど、学歴で評価しようとすると、今の日本では大学卒という学歴は評
価できません。学歴で評価できるとするならば、大学院卒という学歴だけは皆評価するでしょうね。
私だって相手の人が、「大学院卒です」と言われれば、この人はさぞ勉強したんだろうなと思います。
大学院だけは、全員が勉強してるはずなんです。勉強しないと卒業できない仕組みになってい阜ので
す。大学卒業というだけでは通用しないんです。
そうするとですよ、本当の意味で学歴で生きていこうと思うんだったら、大学院を出なけりゃいけ
ない。その大学院に行くために、高校に行かなきゃいけないわけでも、大学にいかなきゃいけないわ
けでもなくなっちゃったんです。だから高校も大学も、真に自分の所の3年間で、あるいは大学の4年
間で、「これだけの力をあなたがたの身につけさせてあげられますよ。」と生徒や学生に約束してい
って、その約束を果たせない高校や大学はもういらない。まあ、私立だったらすぐ潰れちゃうでしょ
うし、国立や公立でも、そういう所にこんなに税金を投入していいのっていう、行政改革の中で真っ
先に、そこを潰されてしまうことになってくる。
皆さん、既にご存じかどうか知りませんが国立大学の教育学部だってどんどん定員を減らしていっ
てるんです。教育学部出たって、学校の先生になれないくらい、学校の先生の募集が少なくなってい
るのに、教育学部をこんなに沢山作って、学生の側からは、教育学部に入ったら先生になれると期待
するじゃないですか。だけど、入ったって二人に一人もなれやしない、そんなんだったら、ここで教
育学部って看板を掲げてること自体が偽りになってしまうから、教育学部に入って、「200全員が教
師になれますよ」と言えないんだったら、入学定員を100人に減らしていかなきゃそれはおかしい。
半分しかなれないんだったら、入学定員を半分にしていかなきゃいけない。そういうように、真にそ
れが価値ある学びの場であるかどうかということを問われる時代になってくる、ということです。だ
から、学校の価値というのは、より沢山大学に入れる学校とか、よりいいと言われる大学に入れる学
校がいい、という時代はもうおしまいなんです。3年間に、よりよい教育を提供するかどうかであっ
て、それは、大学へ進むことではないんです。勿論、3年間一生懸命勉強した結果、大学に進学する
子が多かった、それは結構なんです。大学に沢山入ったからじゃないんです。その3年間どんな教育
をしたか、その高校で過ごした3年間が、その人間の生きる力をどれだけ付けていったのか、という
ことです。だから、「うちの学校は大学に一人も進学しなかったけれども、全員目を輝かせて就職し
て仕事をしてますよ。」という学校がある、「それだけの力をうちの学校では身に付けてもらいまし
たよ」というすばらしい学校だと思います。
学校の価値というものは、その3年間に求められるものを用意していく、だから、「うちは数学や
理科の好きな子が思う存分数学や理科の勉強ができる学校ですよ。」それはそれで結構、○○大学、
理科系の有名大学への進学率が高いよ、ということを売り物にするんじゃなくて、ここでは本当にす
ばらしい理科や数学の勉強ができる学校ですよ。本当にそういう学校だったら、当然、則ちその子達
はより難しい勉強を目指して、大学の工学部や理学部を目指して、ものすごく勉強するでしょうから
結果として大学進学率が上がる。大学に進学させる、就職させるそれは目的じゃない。学校で3年間
何をやって、この学校に15才で入って来た時と、18才で出ていった時はどう違うのかという問題なん
です。これは障害児学校だって同じことです。この学校に来てもらったら、この学校で例えば6年間
あるいは12年間学んでいったら、これだけの力が付きますよ、ということを、お約束してそれを付け
ていく。全部同じなんです、高等学校も障害児学校も、その学校に来て、その学校を出て行く時まで
の間に、どれだけの変化が出てくるのか、うちの学校に来るとこれだけですよ。今までは出たときに
何処へ行くかということでそれを見てしまっていたけれど、入ったときから出て行くまでに、どれだ
け変化があったか、その変化はこうですよということが大事なのです。
予言させていただきますけど、それを言えない学校はなくなっていくと思います。何を、うちの学
校はするか、いろんなことがあっていいと思いますよ。例えば、ふるさとを愛する人間、この町に残
って、この町で、この地方を支えていく人間を作りますよ。うちの学枚で3年間やっていくと、ふる
さとっていいなという気持ちを必ず持ってもらえますよ、というようなことでもいいんです。そのよ
うな学校作りをしていける学校でなければ、成り立っていかない。それは、大学の方が先に現れます
よ。
今、一番ピンチに陥っているのは、ここの高知大学なんかもそうでしょうけど、地方の国立大学で
す。それは何故か、もうはっきりしてきているんですね。地方の国立大学に入ってたって、出てから
就職するのが非常に難しい。東京や阪神などの私立大学に行ってる方が就職に便利だ、就職に有利だ
という話が出てきました。それは何故かというと、これは、別に学校のブランドが高いとか、低いと
かいうことじゃないですよ。ましてや、地方の大学だから入れない、そういう意味じゃないですよ。
それは、こういうことなんです。就職の仕組みが変わったからなんです。昔は、それこそ学歴で採用
してたから、学歴さえよければ、すぐ採用してくれてたんです。例えば、そうか高知大学を出てるの
か高知大学はすばらしい大学だろうと思うから、じゃあ採用しようと言ってくれてたんです。でも、
今は企業が、学歴だけでは採用しません。あなたは、どれくらいのカがあるのか、どんな人間なのか
ということをものすごく詳しく見る訳なんです。ということは、どうなるかというと、自分を売り込
まなきゃいけない。昔だったら書類だけを送って、書類だけでとおってる人もいますよね。例えば、
東京大学法学部卒なんていう書類だけ送れば、どうぞ来てください、なんてことになっていた。でも
今はそうはいかない、あなたに何が出来るのか、一体どのぐらい英語が喋れるのか、一体どれぐらい
コンピューターがいじれるのか、一体どれぐらい人とコミュニケーションする能力があるのか。そん
な有名大学の卒業証書だけで採ってたらね、人と会話が出来ないような人間だったりする様なことに
なるから。
学歴だけで見ていくと心配だから、どんな人間かじっくり話します。どの会社でもそうします。そ
うすると、東京の企業に就職しようと思ったら、東京に居る方が有利じゃないですか。今日来たら、
また明日もきて、と言われて、毎日来いよとか言われますよ、今の採用方法だと。文部省だって、お
役所だって採用するときにはそうです。おいでと言って来たら、今日はある人が話をして、翌日また
来てもらって別の人間が会って、いろんな人間がいろんな角度から見て、この人間はいいですよねと
話をして決めていくからものすごく手間がかかります。だから今、地方の大学の人は東京に何日もホ
テル住まいして採用試験に臨まなければいけないというようなことになる。
つまり学歴だけで採用が、もし本当にあってるんだとするならば、そんな苦労はしなくていいはず
です。この人は、この大学を出ているんだから、ということである程度採用してくれる、そうじゃな
くなってきたからこそなんです。だから、地方国立大学が、今まで黙っていたって学生が集まると思
ってきた部分がある、実際そうだったでしょう。広島県でも勿論そうなんだけど、私もいろんな県で
仕事したことがあるけど、県立学校は、基本的には国公立大学に進学させたいと思いますよね。授業
料の安いところに行かせてあげよう、いや国公立大学はきっといいに違いない、私立はいろんな大学
があるけど、国公立大学は教育水準がきちんとしてるに違いない、ということで国公立大学を奨めて
ましたよね。東京の国公立大学に行かずに、東京の私立大学に行くくらいだったら、地元の国立大学
に行った方がいいよ、水準もきちんとしてるし、どういう大学かよく分かってるし、授業料も安いし
ということを言っていたわけです。それが、必ずしもそうではなくなってきた、つまり大学に行くだ
けで、人生が終わるんだったら結構だけど、大学を出てから何をするかということのために大学に行
ってるわけでしょう。
教育改革の基本理念は生涯学習ですよ。18歳の時にどうなったか、なんて関係ないんですよ。一生
涯を、どんなに幸せに送ったかということですよね。それを、忘れてもらったら困るんです。高校卒
業するときに、○○大学に大勢入ったとかなんとかということなんかも人生の通過点。みなさん、マ
ラソンやってるときに、5キロ地点でトップに立ってる人に、金メダルを出すわけないじゃないです
か。まるで、今やってることは5キロ地点でトップに立てと言って、バアツと全力疾走させているよ
うなものですよ、42.195キロもたない人間が、いっぱい出てきてしまっているんですよ。高校を卒業
した時点で、地元の有名な何とか銀行に就職できたとか、東京のなんとか大学に入れたとかなんて言
ってるのは、5キロ地点での位置取りを競ってるだけの話なんです。末永く、80年、10