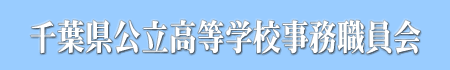この2年くらいで教育をめぐる言葉としてさかんに言われている言葉が3つほどあります。
(1)「崩壊」という言葉
①学級崩壊 ②学校崩壊 ③学力崩壊 ④大学崩壊 ⑤高校崩壊
(2)「総合」という言葉
新しい学習指導要領によって「総合的な学習の時間」の新設、いわゆる総合学科の創設
(3)「学力低下」という言葉
大学の先生方は、日本の子供たちの学力が低下していてこれでいいのかということを盛んに論
議されている。
この3つの言葉は、社会の構造が変化し、物事が過渡期で転漁期であることを象徴する感じがする。
例えば、学級崩壊は伝統的な教育秩序が個性の時代に通用しなくなっていることであり、「総合的
学習」の「総合」は日本の「知」の構造が変質してきたことからきている。かっての日本の大学の学
部は、文学部にしろ法学部にしろ医学部にしろその名前を開いただけで親学問が何であるかというこ
とがすぐにわかった。しかし、現在の環境情報学科、総合政策学科、コミュニティ福祉などとあるが
具体的に何をやるのかすぐには分からない。このように「知」の体系が変わってきている。日本の学
力観が新しい学習指導要領による新しい学力観に変わってきている。
いずれにしても、その背後にあるのは日本の社会システム、価値システム全体が構造的な変革をせ
まられているからである。かってのように標準的でいわゆる粒ぞろいの人材を沢山作れば良いという
時代ではなく、これからは自分で自分の進むべき方向を決定することの出来るカを持つ人材が必要で
ある。従来型の人間像では通用しない。そのために学校のシステムや行政のシステムをかってのよう
な堅いものから柔らかいものへと切り替えていく必要がある。大変つらい作業ではあるが、今強く求
められている。
改革という言葉を考えるとき、プラス面とマイナス面について考える必要がある。プラス面しか持
っていないようなシステムというのは存在しえない。改革というものは、もともとマイナス面があっ
たから改革をするというものではない。当初はプラス面であったものがその経過とともにマイナス面
が目立ってきたのでそれを改めるということである。日本の教育改革もそのような局面にある。
かっては日本の教育は非常に効果的で日本の経済を押し上げ生活水準も高めてきた。世界にも例の
ない速いスピードで高学歴社会を作ってきた。しかし、このような成功の代償として負の作用に我々
は直面している。したがって、中央教育審議会は、ここわずか3年間のうちに5つの答申を出した。ほ
かにも教員養成審議会が3つの答申、あるいは教育課程審議会、保健体育審議会、生涯学習審議会な
ど文部省内のありとあらゆる審議会が矢継ぎ早に論議をすすめ報告、答申、提言をしている。
昭和46年の答申から30年位かけてようやく第三の教育改革の仕上げの段階にきている。日本の近代
学校制度が明治以来130年の歴史を持っているがその3つ日の非常に大きな節目の中にいるのだという
ことを認識しておく必要がある。
現在進められている教育改革は、1984~87年に4つの答申を出した臨時教育審議会の流れにそって
打ち出されているものと理解していただきたい。その主旋律は、自由自立、自己責任の原則である。
すなわち、これからの教育は画一よりも多様に、剛直よりも柔軟に、集権よりも分権に、投機性より
も自由自立を原則として展開されなければならないということと同時に、教育を受ける側の児童、生
徒、保護者の意見と権利を十分に尊重しなければならないということである。
かっては、国家に有為な人材を作るという社会のニーズが優先されたが、これからは個人のニーズ
にも目配りする必要がある。もちろん社会のニーズは当然のことながら必要であるが、それと同時に
個人の--ズにもきちんと対応しなければならないと述べている。このように臨教審はここに大きな
ターニングポイントをふみだした。
現在進められている改革のキーワードをあげれるならば、次の言葉である。
(1)個性化
目標としての個性化、子供たちの自己実現
(2)自由化
子供たちの個性を作っていく手段としての自由化、そのひとつとして規制緩和、発達段階に応じ
た学ぶ自由
(3)多様化
上記の目標としての個性化、手段としての自由化、そしてその経緯としての多様化
上記に引き続くキーワードとしては「生きる力」という言葉である。これも3つのことが言えると思
う。
(1)自ら学び、自ら考える、主体的に判断し、行動し、より良く問題を解決する力
(2)自らを律し、他人と協調し、他人を思いやる心、豊かな人間性と社会性
(3)たくましい身体と健康
これらを別の言い方に置き替えると、
(1)組織の外でも生きる力
これからは横ならび、ことなかれ、ぬるま湯などで判断を放棄することでなく、組織をやめたあと
でも別のところでボランティアなどをして生きる力がなければ通用しない。
(2)国境を越えて生きるカ
グローバルリズムが発達して国境を越えて生きる力がなければ日本の社会は活性化していかない。
(3)他者ととも生きるカ
選択と競争という世界をバランスよく組み合わせていけるカ
このような新しい学力観に基づく「生きる力」をもととした知の統合化と同時に学びを通して学び方
を学ぶ、すなわち、生涯を通して学習していく社会のなかに学校がきっちりと位置づけられること。
どんな激しい変化がやってこようとも、それにしなやかに、かつ、したたかに生きていける力を養う。
そのためには、頭をう-んと柔らかくしておく必要がある。それを保障するには、学校システムその
ものどころか、行政を含めた教育システム全体をう-んと柔らかくしておく必要がある。
実はこの生きる力という新しい学力観は大学の方とのつながりを持ち始めた。/ト中高と大学は切断
されていた。入学試験でかろうじてつながっていた。おそらく、大学入学者はここ2、3年で50%を越
え、2009年には大学の入学定員と大学の進学希望者の数が一致すると言われている。大学入学を希望
するものが全員大学に入れる時代がやってくる。そうなると高校と大学とは、かってはステップがあ
ったけれども平面となり地つづきの関係となる。したがって、若者たちは高校から大学へと平面を移
動することとなる。そのため大学審議会は「接続に関する」5つ日の答申の中間報告を出した。また、
21世紀の大学像として「競争的環境のなかで個性あふれる大学を目指して」を出した。 そこでは、
これからの大学は学生たちに課題探求能力を育成することを最重点に置くというものである。この課
題探求能力は、小学校、中学校、高等学校での課題発見や課題解決型学習の積み重ねなくしては達成
できない。つまり、一本の碑につながって始めて生きるカというものに結実するものである。さて、
次に個性化型についてです。子供達の個性を重視し、それを実現するためのひとつとして総合的学習
の時間の創設です。また、選択の拡大です。教科の枠の中ではあるが自分の個性にあった課題を選び、
総合的な考え発展的学びや交流的な学びを通して選択的能力を高め、それによってこれから大きな課
題となる中高一貫教育へと発展させてゆくことである。さらに、これを含めた特色ある学校づくりへ
とつなげてゆかなければならないと考えます。
これからの特色ある学校は、子供達が個性的に学べるための個性的なカリキュラムを持っている学
校です。今回の学習指導要領の改定によって学校の自由度はかなり拡大しました。そのひとつは、一
単位当たりの授業時間枠の撤廃と連続的集中的に授業を組むことの自由です。例えば、毎日30分の英
語の時間を設けたり、午後の授業を連続して総合学習をやったり、情報関係の授業を一学期の間に集
中的にやってしまうなどのことが出来ます。すなわち、カリキュラムを自分達がデザインする。総合
的学習などは、当然教科書がないので自前の教材を生徒達と一緒に作る。あるいは、学校外のいろい
ろな人達の意見を開いて授業を設計してゆく。いわゆるコーデイネイトしてゆく必要がある。しかし
その結果については自分達が責任をとる。自己責任(アカウンタビイリテイ)の明確化です。そうい
うことが求められる時代が来るし、来ています。
地方教育行政の今後の在り方について98年9月に答申が出ました。この答申は、単なるお題目やス
ローガンではありません。新聞記者風にう-んとラジカルにはしょって乱暴に言いますが、これから
の教育委員会は学校支援委員会に変えてゆくというように置き換えて考えると概ね間違っていない。
すなわち、管理から支援へと教育委員会は変わってゆく。利用しやすくなる。これまでの文部省と学
校とを図式化する
と最上位に文部省があり、その下に都道府県教育委員会、さらに、その下に地方教育事務所や市町
村教育委員会があり、最下位に学校があり、それだけでなく最後に地域があり、多くの市民があると
いうことであった。
今度は、学校が最上位になり、その横の関係で地域があり、市民や企業があります。その下に市町
村教育 委員会、地方教育事務所が学校を支える形であります。さらにその下に都道府県教育委員会
そして、一番根底部分、基幹部分に文部省があり、それらを束になって支える、下支えするというふ
うに変わります。これらを実現するために、これまで学校を縛ってきた規則、統制、法律など可能な
限りゆるめる。あるいは、物によっては撤回するということが進められています。
校長の権限の強化もその一つです。例えば、人事の側面や予算の側面です。今までは予算の費目は
細々枠がはめられていたが、それらを切り離して使うことが出来るようにする。あるいは、教育活動
においては教師集団の裁量をどんどん拡げてあげる。そのことによって学校の主体性や自主性・自律
性を確保でき、それによって創意工夫が飛躍的に拡がりその結果として特色ある学校づくりが出来る
ということになります。かつての上意下達の関係から180度の転換となります。130年間の日本の行政
システムの歴史の中で、実は大変不慣れなことをやらなければならないことになります。日本の社会
システムそのものも構造的歴史的な転挽を余儀なくされている中、学校もその例外ではないというこ
とです。
文部省が出した教育改革プログラムの中で、学校支援ボランティア推進ということが述べられてお
ります。ほんの10年前には考えられない言葉です。このことは、学校の外とのパートナー’シップ抜
きではこれからの教育はなし得ないと言っているわけです。例えば、地域社会の中では企業がありま
す。その中には社員がおります。この社員をボランティアとして、あるいは非常勤講師としてお願い
する。また、ボランティア団体を特定非営利活動法人として法人格を与えるNPO法が成立しましたが
これらのボランティアを含めて学校を支える組織を作らなければならない。すなわち、第1セクター
は行政、第2セクターは企業、第3セクターは市民ボランティア組織ということです。この3つのセク
ターがパートナーシップを組みいろいろな課題の解決に力を発揮してもらうということです。このこ
とは、95年1月の阪神淡路大震災のときにはっきりと経験しています。マスコミとボランティアは150
万人集まったと言われております。