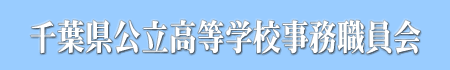●研究活動
事務職員会創立50周年によせて支部活動
船橋支部
津田沼高校 飯 田 和 夫
11年度に知事部局より教育庁に出向し、勤務年数自体もまだ5年に満たない私のような若輩者が、
今回、事務職員会の50周年記念誌に寄稿することとなりました。経験も判断能力も乏しく、自分の
職務を全うすることだけで精一杯の毎日です。
事務職員会が発足してから50年。実に半世紀です。おそらく手探りの状態からスタートし、その
中で諸先輩方が努力に努力を重ね、多くの試行錯誤を積んで、現在に至る体制を構築されたものと思
います。
思えば私たちが小・中・高と一貫して民主的な教育を受けられたのも、確立され、安定した学校の
体制があればこそのものだったでしょう。
しかし昨今の社会情勢を鑑みると、戦後以来のいわゆる「常識」がことごとく崩れ、価値観が大き
く揺れ動き、また多様化しており、従来の施策や慣例だけでは対処しきれない時代にさしかかってい
ます。「学校のあり方」そのものがどうあるべきなのか、そういった議論が盛んに行われ、また模索
されている時代です。
私たち学校教育に携わる事務職員もそういった社会情勢に的確に対応し、これからの学校教育をよ
り良いものとするため、先代に続き努力を積み重ねなければならないと自覚しております。
先述しましたが、私たち若手の職員は、どうしても経験や判断力、知識に乏しく、諸先輩方にお世
話にならざるを得ません。しかしその分、「こういうものだ」という固定観念や慣例にとらわれない
視点を職場に向けられ、またこれからの時代に必要とされるコンピュータやインターネット等の電算
・情報化にいち早く対応でき、戦力になれるものと自覚しています。またそれが私たちの責務である
と自覚しています。
もちろん、仕事の基本はあくまで「人」であると思います。コンピュータ万能のように言われます
が、いくら機械が進歩して、電算化が進もうとも、それに頼りすぎ過信すれば、基本的な部分で判断
ミスを起こしてしまいかねません。諸先輩方に基本的な仕事の進め方を教わりつつも、コンピュータ
等で処理できる点については合理化を進めるというようなバランス感覚が大切だと思います。
さる11年11月10日に創立50周年の記念研究大会が開催されました。私は大会に出席するの
は初めてでしたが、年金制度や、学級減に伴う普通教室(余裕教室)の有効利用の仕方、介護休暇制
度等、我々が現在直面している、また遅かれ早かれ直面していく諸問題について、研修委員の方々は
実に深く掘り下げて研究されていました。私自身も厚生委員として、親睦会等の実施に参加させてい
ただきました。委員の活動を通じて、他校の状況のお話を伺える機会もあり、「横の繋がり」を意識
できるとても良い機会となりました。今後もこういった研究発表の場と親睦の場がより生かされるも
のと期待しています。
価値観が多様化し、複雑化している時代です。こういう時代だからこそ、事務職員相互の連携を大
切にしながら、これに対応していかなければなりません。そして、先代の先輩達から引き継いだよう
に、次の50年に向けて、努力を重ねたいと思います。