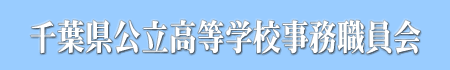●研究活動
支部活動「学校」という職場に勤務して
海匝支部
銚子養護学校 多 田 廣 子
事務職員会が発足してから、半世紀を迎えることができたことは、とても素晴らしいことです。会
員の一人として、心よりうれしく思います。おめでとうございます。
その50周年記念誌に掲載する原稿の依頼が、どのような理由からか知りませんが、私の所に廻っ
てきてしまいました。何を書いたらよいのかと悩んでしまいましたが、高校卒業後、直ぐに就職した
「学校」という職場について、私なりに感じたことを書くことにしました。
採用されたのは昭和43年です。ソロバン持参で勤務しました。ばつぼつ電池式の卓上計算機が出
始めた頃でもありましたが、まだソロバンを使っての計算が全盛で、会計をする人にとっては必需品
でした。
それが今では、携帯電話・ノートパソコンの「メディアスーツ」を身にまとう時代になりました。
会計伝票も、手書きの時代からカーボン複写、そして県下一斉の電算処理と変化しました。印刷物
もガリ版を使わなくなってからもうだいぶ経ちました。
伝達方法も郵便・電話からFAXへと発展しました。2000年を期として給与事務も電算化し、
各校で入力・送受信・出力と全て行うようになりました。
情報技術の進歩により、職場を取り巻く環境は、ますます変化することでしょう。変化に適応でき
るよりにこれからも一層の努力が必要だと思います。
私が採用された頃の高等学校数は、現在の約半分でしたから事務職員の数も少なかったようです。
職員のレクレーション大会も、生徒が夏休みになった時に、体育館や運動場を借用して行われました
昔は、ソフトボールとバレーボールは誰もが手軽に楽しめるスポーツの代表でした。いまでは、サッ
カー・卓球・水泳等いろいろなスポーツが広まり会員の趣味も多様化してきました。又、多数の事務
職員が遠方より集まる事により生じる諸間題が増えて来たのでしょう。
今風に言えば、地方分権化とでも申しましょうか。レクレーション大会に替わる行事を各支部が行
うことになりました。ちなみに海匝支部では、ボウリング大会を行いました。上手な人も下手な人も
それなりに楽しみました。
私が卒業した学校、職場としての学校、ふたりの子供が通学した学校と立場が異なれば、学校に対
する感じ方もそれぞれ異なります。
又、学校事務職員の採用方法が一本化し、人事交流も頻繁になるに伴い、学校事務職員として働く
人の考え方も多様化して行くことでしょう。
2002年からの週5日制、単位制高校、中学高校一環教育など導入により、これからは学校が大
きく変わると思います。
いろいろな考え方や情報が氾濫するなかで仕事をするとき、何をどのように選択・処理するのか迫
られている状況だと思います。私の勤める「学校」という職場は、教育行政組織の一部ですので、当
然のことですが、規則を基にして、物事を処理するように心がけなければいけないと思っています。
「学校は、次世代への知識を伝達する役割を担っている」と考えられています。日本という国家があ
るかぎり学校教育は、存続するでしょう。微力ではありますが、学校としての役割がうまく機能する
ように、これからも努力して行きたいと考えています。
又、公立高等学校事務職員会がますます発展・維続できることを願っております。