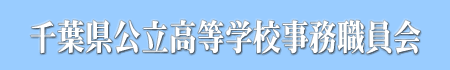今 昔
第15代会長 岩井 幸治
職を辞して丁度10年が経ちました。
今朝の千葉日報の一面には、海外の修学旅行解禁が、昨日は高校の統廃合検討が大きな活字で報じ
られています。
られています。
朝日新聞は教育改革国民会議の座長に江崎玲於奈氏起用を報じています。
小渕内閤が目指す改革の一つとはいいながら教育問題はいろいろと取沙汰されています。
振り返って、私の現職時代は今ほどではなかったかもしれませんが、それでも結構変わりました。
昭和49年 コンピュータの導入による出納室の発足
昭和53年 入学寄付金の廃止
昭和56年 4週5休のスタート
昭和57年 授業料の口座振替開始
給料計算の一元化開始
などが挙げられますが、なんといっても生徒急増対策は凄まじいものでした。
昭和50年代は毎年6~7校が開校していったように記憶しています。
特に、昭和55年には幕張に全国でも始めてという3校の集合高校がお目見えしました。
風が吹けば挨まみれ、雨が降れば泥沼の仮設校舎もなつかしい思い出です。
私は、こんな嵐のような急増期が一段落した時に事務職員会の役職.を穢させていただきました。
菲才ですが「研修と親睦」をモットウに楽しく仕事をさせていただき、皆様のご支援・ご協力によ
って恙なく職を全うすることができました。
って恙なく職を全うすることができました。
あらためて感謝の気持ちが込みあげてまいります。
ところで、今度は開校の時代から統廃合の時代ですから、まさに隔世の感があります。杜会情勢に
対応する必然性かもしれませんが、増やすより遙かに難しい問題だと思います。
対応する必然性かもしれませんが、増やすより遙かに難しい問題だと思います。
一方、教室の中では、心のケアーの必要な子が増えています。
茶髪に携帯電話を持ち、簡単に頭にきたり、キレタリする高校教育は、何をどうなすべきなのか?
そして、そのための事務職員の役割は何なのか? まさに試練の時代です。
そして、そのための事務職員の役割は何なのか? まさに試練の時代です。
こんな時代に私立高校に勤務する私は、時に因果なことだと嘆くこともあります。
私立の学校は経営という一面を持っているので、収入を考え支出とのバランスを保たない限り破滅
です。
です。
生徒の減少は、長いこと公立の滑り止めに甘んじ、その上この不景気で、授業料の高い私立高校に
とっては死活問題です。
とっては死活問題です。
授業料が高い分、何か付加価値を付けなければと四苦八苦の毎日ですが、幸い健康には恵まれて元
気で働いております。
気で働いております。
公立は公立で、私立は私立で、叡智と努力を結集して厳しい状況を乗り超えましょう。
事務職員会のますますのご発展と会員皆様方のご健勝、ご活躍を祈念申しあげます。