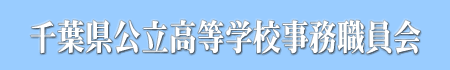奥山浩先生の豊富な知識と経験を基に講演をされました。その概要は次のとおりです。
「教育改革の方向」講演の概要
1 共済年金について
少子高齢化社会が進む中で、地方公務員共済組合全体では、昭和50年には8人で1 人の年
金受給者を支えていたが、平成9年度では2.5人で1人を支えており、公立学 校共済に限っ
て言えば、1.9人で1人を支えるている。
金受給者を支えていたが、平成9年度では2.5人で1人を支えており、公立学 校共済に限っ
て言えば、1.9人で1人を支えるている。
年金財政への対応として、年金支給開始年齢の段階的引き上げ、支給額の減額、定年 延長等
の対策が検討されている。
の対策が検討されている。
2 千葉県の財政状況について
法人2税の大幅な落ち込みによる財源不足は、平成11年度当初1,460億円が見 込まれ、
滞納税の徴収、人件費の削減等により対応した。さらに9月県議会において補 正を行ったが、
なお160億円が不足している。千葉県の予算規模からみると、今後4 07億円以上の赤字決
算になると財政再建団体となる。財政再建団体となると、全てに おいて国の指揮命令を受け、
地方債の発行ができなくなる。また、国の水準以上のもの は削減されることとなり、補助金の
カット、計画的人員整理などが行われる。今後、一 層の行財政改革が必要である。
滞納税の徴収、人件費の削減等により対応した。さらに9月県議会において補 正を行ったが、
なお160億円が不足している。千葉県の予算規模からみると、今後4 07億円以上の赤字決
算になると財政再建団体となる。財政再建団体となると、全てに おいて国の指揮命令を受け、
地方債の発行ができなくなる。また、国の水準以上のもの は削減されることとなり、補助金の
カット、計画的人員整理などが行われる。今後、一 層の行財政改革が必要である。
3 教育状況について
いじめに関する件数は減ってきたが、昨今は生徒間暴力、器物破損などの校内暴力や 授業が
成り立たないなどの学級崩壊の問題が増加している。教師の指導力不足という調 査結果もある
が、問題解決は簡単ではない。
成り立たないなどの学級崩壊の問題が増加している。教師の指導力不足という調 査結果もある
が、問題解決は簡単ではない。
戦後教育のウイークポイントとして、①「心の教育」が劣っている。②基本的生活習 慣の欠
如。③勤労体験学習の不足。④自然に親しむ学習の機会が少ない。などがある。
如。③勤労体験学習の不足。④自然に親しむ学習の機会が少ない。などがある。
現在の日本の教育レベルは高いが、画一的・排他主義・学歴偏重や非国際性を打破す ること
が大事である。
が大事である。
4 教育改革について
いままでの日本の大きな教育改革は、明治5年の学制、昭和22年の6・3・3制発 足、昭
和46年の養護学校の義務化、高校の多様化などがある。
和46年の養護学校の義務化、高校の多様化などがある。
昭和59年に設置された臨教審からは、①個性重視の原則。②生涯学習への移行。③ 変化へ
の対応などが答申された。
の対応などが答申された。
不易流行という理念があるが、時代が変わっても変わらないものはきちんと教え、そ の上で
変化する社会に対応できる教育をする必要がある。
変化する社会に対応できる教育をする必要がある。
作家の遠藤周作氏や椎名誠氏の場合も、才能を見出され個性を伸ばした一例である。
教育改革に関する課題をまとめた国の「教育改革プログラム」の中で、特に重要な事 項とし
て、①心の教育。②個性の伸長に応じた多様な選択ができる学校制度の実現。③ 現場の自主性
を尊重した学校づくり。④大学改革。がある。
て、①心の教育。②個性の伸長に応じた多様な選択ができる学校制度の実現。③ 現場の自主性
を尊重した学校づくり。④大学改革。がある。
これからは、学校に教育成果が求められるようになり、学枚はその成果を保護者や地 域に説
明する責任がある。
明する責任がある。
我が国が21世紀に科学技術や文化立国を目指すには、社会的システムの基盤である 教育を
さらに充実させていかなければならない。そのためには、教育改革が不可欠であ る。国でも、
「教育改革国民会議」をつくる動きがある。ここでは、6・3・3制の是 非についてまで論ぜら
れるようである。千葉県でも、千葉県の教育長期ビジョン「千葉 の教育 夢・未来2025」
が策定され、その中で、教育改革にカを注ごうという趣旨 で動き出している。
さらに充実させていかなければならない。そのためには、教育改革が不可欠であ る。国でも、
「教育改革国民会議」をつくる動きがある。ここでは、6・3・3制の是 非についてまで論ぜら
れるようである。千葉県でも、千葉県の教育長期ビジョン「千葉 の教育 夢・未来2025」
が策定され、その中で、教育改革にカを注ごうという趣旨 で動き出している。
以上、国や千葉県でどういう方向性をもって教育改革を進めているか、少しでも認識 しても
らえれば幸いである。