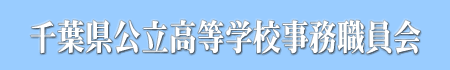地方分権、あるいは学校の自主・自律性の確立について、文部省がなぜ言っているかということに
ついて、教育改革プログラムで示しております。このことは橋本内閣時代に6つの改革のひとつとし
て教育改革を定め、その改革が具体的にどのようなスケジュールで進んでいるかを発表したものです。
その中の4つの柱が、実は学校の自主性・自律性の確立ということです。地方分権あるいは学校の
自主・自律性が大事かということは、ひとつは国全体の考えとして地方分権が必要であること。これ
は明治以来の、あるいは戦後改革に続く第3の改革です。長年続いてきた中央集権国家を地方分権に
改めるということです。 主旨のひとつは、縦割行政の弊害を是正することです。一番分かり易い例
として、コミュニティセンターや老人ホームを造る場合、一方は自治省と他方は厚生省とそれぞれ建
物の基準が違い、そのために地方の総合的な発展が上手く行かず、地域のコミュニティの形成がなか
なか難しいことがあります。
これなどは、縦割行政の問題点を抜本的に改善しないと地方の豊かな行政ということが出来ないひ
とつです。
ふたつ目は、激しく変動する国際社会のことです。日本の製造工場が海外の台湾や韓国にもあり、
あるいはその市場はアメリカ、東南アジアにあり、最近の東ティモールの動きなど世界のいろんな動
きが我が国に直接影響してくる時代です。このような中、国はもっと国本来のやるべきことに専念し
その機能を強化し、国は国の責任をちゃんと果たしてゆくべきだということです。
三つ目は、東京一極集中の弊害です。一生働いても家が持てない、あるいは家を買っても通勤に2
時間半かかるため結局東京に単身赴任という形になってしまう。こういう人間の生活は、本来の人間
らしい生活ではないと問題として指摘されている。また、地方で市民文化祭をやりますと、踊りを踊
っている方も平均年齢が60才か70才、それを見ている人も60歳前後ということで急速な高齢化でコミ
ュニティ自体が崩壊するのではないかといわれている。したがって、分散型の国家を形成しなければ
ならない。
さらに、これまでの我が国はどちらかというと生産者中心で豊かな国になりたいということで、い
かに経済を発展させるかという視点での国家だったと思います。これからは、生活者の視点で地域を
つくってゆく、あるいは我々の視点で社会を形成してゆく必要がある。したがって、地域の最も身近
な、また、生活者に最も身近な市町村、さらには都道府県教育委員会が中心になって行政を推進する
ことが必要だろうということです。このように、色んなことが言われている地方分権が国全体として
進められてゆくことになったわけです。
このように文部省は文部省としてこれからの教育は地方分権でゆこうということで、平成元年の学
習指導要領の改訂に伴いまして、「新しい学力観」を、この新しい学習指導要領に導入いたしました。
このことによって、これまでの危機に瀕した教育から子供が自ら考え主体的に判断し、行動できる力
の育成を重視するという基本的な部分での方向を転換し、学校教育の基調を変えてゆくということで
す。
この考え方は、基本的に申し上げると、これまでは西欧諸国に追いつき追い越すんだから、出来る
だけ西欧の既存の知識・学問体系をいかに子供達に効率的に効果的に伝えるかということが使命だっ
たけれども、これからは子供達が生きてゆくために必要な学力、自ら学ぶという力をつけてやること
である。そうなると、むしろ学ぶ側子供の視点にたった教育をより重視すべきではないかということ
になります。
これまでは、どちらかというと社会の視点にたった教育であったわけですけれど、これからは子供
ひとりひとりの興味関心、能力資質を見つめながらその子供達の夢と希望を充実させるような教育活
動を展開させていかなければならない。このことは、当然のことながら子供の願い、子供を取り巻く
地域社会というものをとらえた教育をしなければならないということです。
全国の先生方や専門の学者の方々の意見を集約して高等学校教育をどうしようとしても十分ではな
いのであって、できるだけ地方分権をしてそれぞれの地域において、子供の視点、いや、生徒の視点
で教育活動をしてゆく必要があり新しい心の教育を実施するという観点にたつと、必然的に学校に教
育の中心があり、自主的に自律的な教育をやらなければならないということです。このような教育を
支援する教育委員会の体制を整備しなければならない。
現在、都道府県教育委員会や各県立学校事務職貞の方々の仕事ぶりを伺いましても非常に充実した
人材、あるいは、体制が整っていると思います。これから分権をしても、大いにカを発揮してもらえ
ると思います。
次に総論はそれでいいとしても、具体的にどこを変えればいいかということですが、ひとつは、分
権一括方を7月に上程し、色んな改定を行いました。その中で大きな改定事項のひとつは機関委任事
務の廃止です。
都道府県全体の7割から8割、市町村の事務の3割から4割は機関委任事務であるといわれております。
その機関委任事務とは本来国の業務であるものを知事に国の機関の一員として仕事をしてもらってい
るという制度です。この制度は、結局は地方公共団体でありながら国の指示に従って仕事をするとい
うことです。その結果、場合によっては地方議会等のいろんな観察がその事務の執行についてのチェ
ックが十分に行き届かないという状況になっており、これがどうも上意下達の風潮を生んでいたので
はないか、あるいは、責任の所在が不明確になり勝ちだったのではないかと言われております。
この機関委任事務を廃止して、地方公共団体の事務を自治事務という本来地方公共団体がやるべき
事務と、法定受託事務といいまして法律に基づいて、国が本来果たすべき事務ではあるけれども、事
務の性質上もっと地方に近い観点でやっていった方がいいのではないかということで、そういう事務
とに分類したわけです。
このように地方に国の事務をお願いする際は、当然法律の根拠がいります。それに伴って文部省関
係では105の機関委任事務がありましたが、約55%の機関委任事務を自治事務に変更いたしました。
そして残る41の事務について法定受託事務となりました。
そのぶん分かり易い代表例を申し上げますと、教員免許状の授与は自治事務となっております。す
なわち、教職員検定普通免許状で採用することが出来ない場合に限って、教育職員検定によって、臨
時職員免許状を授与するということについては自治事務になっております。
さて、今回の改定に伴って大事な点を申し上げたいと思います。それは関与についてです。国が都
道府県の色んな行政に助言をする、あるいは助成をするということが関与ですが、これについては一
般的な原則が地方自治法に書かれております。それは三つの原則があります。丁つは法定主義の原則
二つ目は一般法主義の原則、三つ目は法定透明の原則です。
法定主義の原則は、関与、たとえば文部省が都道府県教育委員会に何か話をする、助言をするとい
うのは法律又は政令のそれに基づく根拠を存するということです。いわゆる行政事務のなかで国が都
道府県に助言をするというような事務は、必ず都道府県の自主性・自律性を阻害するものではない。
だから、必ずしも法に根拠が無くても、関与できるんだとこれまでの古い行政法の解説ではそう書か
れていたと思います。しかし、もしそういうことをしていると国は必要以上に都道府県に関与をして
しまう。国が都道府県に関与する場合は、きちんと法律に根拠が必要ですよというのが法定主義の原
則です。
次に一般法主義の原則です。関与に関わるルールは、できるだけ一般的な法律である地方自治法に
一元的に書いておこうというのが一般法主義の原則である。例えば、これまでは地方教育行政組織及
び運営に関する法律よりは、地教行法を見ればだいたい教育委員会あるいは教育委員会と学校との様
子が分かるというのがこれまでだったと思います。
しかし、これからは地方自治法を十分に日を通していただいて、それでもよくわからなかった場合
は、教育委員会あるいは知事部局の担当の方とよく意見を交換していただくこと。なかなか全体が見
えないときはそうして戴きたいと思います。
たとえば措置ということについては、これまでの考え方として、教育行政というものは、各地方公
共団体の当局がそれぞれ主体的に自主的に法律に基づいてやればいいんだということであったが、し
かしながら、地方公共団体の教育行政の処理が不明確で、かつ、法律によっても適正であるという保
障が必ずしも得がたい事情がおこりうると予測しなければならない場合は、文部大臣が都道府県に対
して、こういうふうにしなさいという措置要求をする。これがなくなります。
ところがこれまでは地方自治関係としては地方自治法上は、例えば厚生省と都道府県関係の例で言
えば内閣総理大臣が全体的な対応の中心であるということで地方公共団体に村し内閣総理大臣より措
置をするということであった。しかしながら、文部大臣だけが自治法上の原則からはずれ、特別文部
大臣直接に都道府県教育委員会に指示ができる。
このように文部大臣の権限が強かったのですが、こういう規定はバランスを失するのではないかと
いうことで改正されました。地方自治法245条の4では各大臣が文部大臣も労働大臣も通産大臣もそれ
ぞれの所掌事務についてそれぞれの地方公共団体に対してこういうふうにしなさいと措置の要求につ
いて具体的な指示をする。「各大臣は・・・…求めることができる」というふうに改正になりました。
このように今回改正によって措置要求が無くなったというふうに勘違いされている方々がいないわけ
ではないので一言申し上げました。以上が一般法原則の措置でございます。
それから一般法主義の原則のもう一つは、関与について、その目的を達成するためには必要最小限
でなければならない。地方公共団体の自主的自主性を十分に配慮しなければならない。こういう文言
が地方自治法に書かれております。
三点目には、公正透明の原則です。文部省が都道府県にお願いする場合の関与の手続きについては
例えば、指導、助言、援助というものが都道府県から求められた場合は、書面でもってきちんとやら
なければならない。あるいは、それを行う場合の審査基準についても公表しなさい。また、それを処
理する処理機関を設置し、一定の期間内に処理するルールを定めるということ。さらに、手続き面に
ついて国が必要以上に都道府県に関与しない。そういう改正がなされております。
さて、このように今回の地方分権一括法で抜本的な改正が図られた結果、それに伴う「地方教育行
政の組織及び運営に関する法律」の改正や、「中教審答申主要事項と必要な措置」による様々な関連
法案が提出され一部成立し、今後さらに成立するものを含めて、大きな制度改革が進行中である。例
えば、高等学校の通学区域の設定についての一部変更、校長の資格についての改正、研修休業制度の
創設、学級編成の弾力的運用などです。